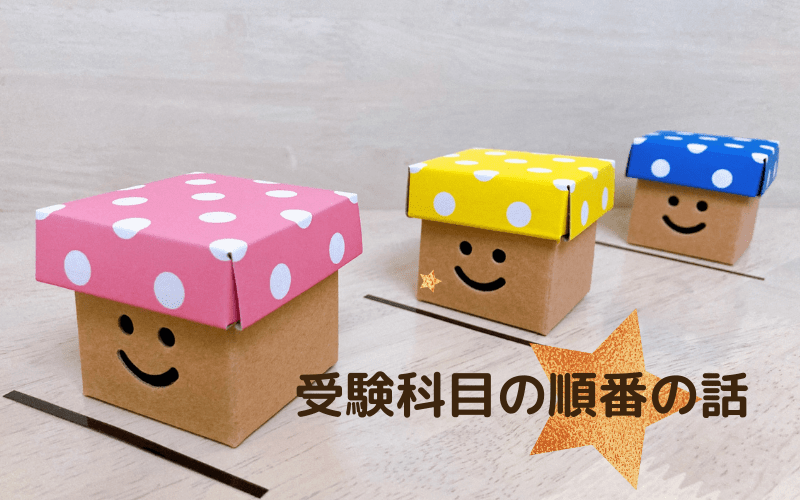税理士試験を受けようと決めたはいいけれど、どの科目から受験しようか、
まだ考えている最中ならこの記事は参考になるかもしれません。
税理士試験を合格するために必要な科目数は
税理士試験合格に必要な科目数は
会計科目2科目
税法科目3科目
の合計5科目を取得する必要があります。
税理士試験のメリットとして
一度合格した科目は生涯有効なため、科目の有効期限などはありません。
そして税理士試験は1科目ずつ受験できます。
期限がないので社会人でも取り組みやすい国家資格と言われています。
取り組みやすいのと合格するかどうかは別の話ですし、
期限がないため、違う角度から見れば長期化しやすいともいえます。
そんな税理士試験ですが、やはり5科目あるのでどういう順番で
受験するのがいいのか迷いますよね。
ここではいくつかのパターンを見ていきたいと思います。
受験科目の順番はどんなパターンがあるのか
いくつかの順番をあげてみます。
1年目:簿記論・財務諸表論
2年目:法人税法又は所得税法
3年目:その他の税法2科目
1年目:消費税法
2年目:簿記論・財務諸表論
3年目:法人税法又は所得税法
4年目:その他の税法1科目
1年目:簿記論
2年目:財務諸表論
3年目:法人税法
4年目:その他の税法2科目
1年目:消費税法
2年目:財務諸表論
3年目:簿記論
4年目:法人税法又は所得税法
5年目:その他税法1科目
1年目:消費税法・その他の税法1科目
2年目:法人税法又は所得税法
3年目:簿記論・財務諸表論
いくつかのパターンをあげてみました。
組み合わせとしてはもっとあります。
通常と言いますか、多くの人が初めて税理士試験にチャレンジするときは
「簿記論・財務諸表論」から始める場合が多いです。
あとは、「消費税法」から始める人もいます。
この辺は好みもあると思いますし、何の科目を勉強したいかにもよると思います。
受験する科目の順番を決める時、何を重視するのか
初めて受験するときはあまり深く考えずに
学校で進められたから、簿記論から始めましたー。
簿記論と財務諸表論の2科目は内容が被るから一緒がいいよ!
と言われたから始めましたー。
なんてパターンもあると思います。
実際に同時学習してみるとわかりますけど、まー時間がない。
5月以降の直前期と言われる時期なんてテストばかりで2科目分の復習が終わりません。
しかも点数なんて全然取れなくて、
周りのみんなはめっちゃ点数いいから一人で落ち込むという…(;’∀’)
なかには優秀な人もいて1年目から2科目、3科目合格される方もいます。
個人的にはそんな超人的な人はまれかと思います。
実は5月から始まる直前期は、初学者も経験者もみんな一緒に学習していく事になります。
なので、隣の席の点数がめっちゃいいあの人は、
もしかしたらもう何年も簿記論の勉強をしてるかもしれない…
と、思えば少しは気が楽になるかも٩( ”ω” )و
なので受験する科目の順番というのは、
1年目に約1年間学校のスケジュールに合わせて勉強してみて自分はきちんとできたのか。
環境によっては忙しすぎて勉強の時間が取れなかったとか
見えてくるものがあると思うんです。
本試験が終わって、自己採点してみて
学校へ今後の方向性について講師に相談する人もいると思います。
講師のお話は一つの参考として聞いておいて
じゃあ自分はどうしたいのか。
8月中には2年目以降の事を考えておくのがいいと思います。
はじめは、
1年目:簿記論・財務諸表論
2年目:法人税法又は所得税法
3年目:その他の税法2科目
↑この順番で受験するつもりだったけど、
簿記論はボーダー以下だから来年も受験
財表は合格圏内だからもしかしたら合格できるかも!?
という状況なら2年目に簿記論と法人税法などの
ボリュームの大きい科目は大変なので違う税法にしよう。とか。
合格発表までは新しい科目をインプットしておいて合格発表の結果次第でまた簿記論に戻る。
なんてこともあります。
あとは自分の興味のある税法から勉強するのもアリです。
なぜなら1年目って一番やる気のある時なので興味のある科目なら尚更学習も進みそうですよね!
と、ここまでは5科目合格して税理士資格を取得するお話でした。
この後、もう一つの選択肢をお伝えします。
大学院を出て税法2科目の免除を狙う
もう一つの道として、
大学院を出て税法2科目免除を狙う
という方法があります。
この税法2科目免除ですが、
通常だと必須科目の法人税法又は所得税法のどちらかを取得しなければいけません。
しかし、大学院で2科目免除を狙う場合はこの2科目の
どちらかを合格していなくても大丈夫なのです。
そのためか何故なのかはわかりませんが、大学院免除を目指す人も結構多いです。
そうすると受験する科目も
以上の3科目でいいので受験する順番を気にするというよりも
1科目の税法科目を何にするかが重要になるかもしれません。
要は合格できればいいわけですよね。
大学院免除の人が受験する税法科目としては
この辺が多いと思います。
消費税法は実務でも使用しますので学習しておいた方が有利です。
固定資産税は、一つの計算ミスですべてが終わるので正確な計算が必要です。
国税徴収法は、計算問題はなく、理論のみなので理論が好きな人
覚えるのが苦にならない人はおすすめです。
ただ、国税徴収法は実務的に必要かというと
ちょっと微妙なのであくまでも税理士資格を取る!
という目標のためと割り切ってしまってもいいと個人的には思います。
まとめ:税理士試験の受験する科目の順番は個人的には学習したいものから!
税理士試験の受験する科目の順番についてお伝えしました。
何が正解なんてありません。
要は合格できればいいのでその時の状況もありますし、
覚えやすい理論も人によって違ったりします。
書店で理論のポケットテキストが売っているので
少し読んでみるのもいいかもしれません。
少しでも参考になれば幸いです。